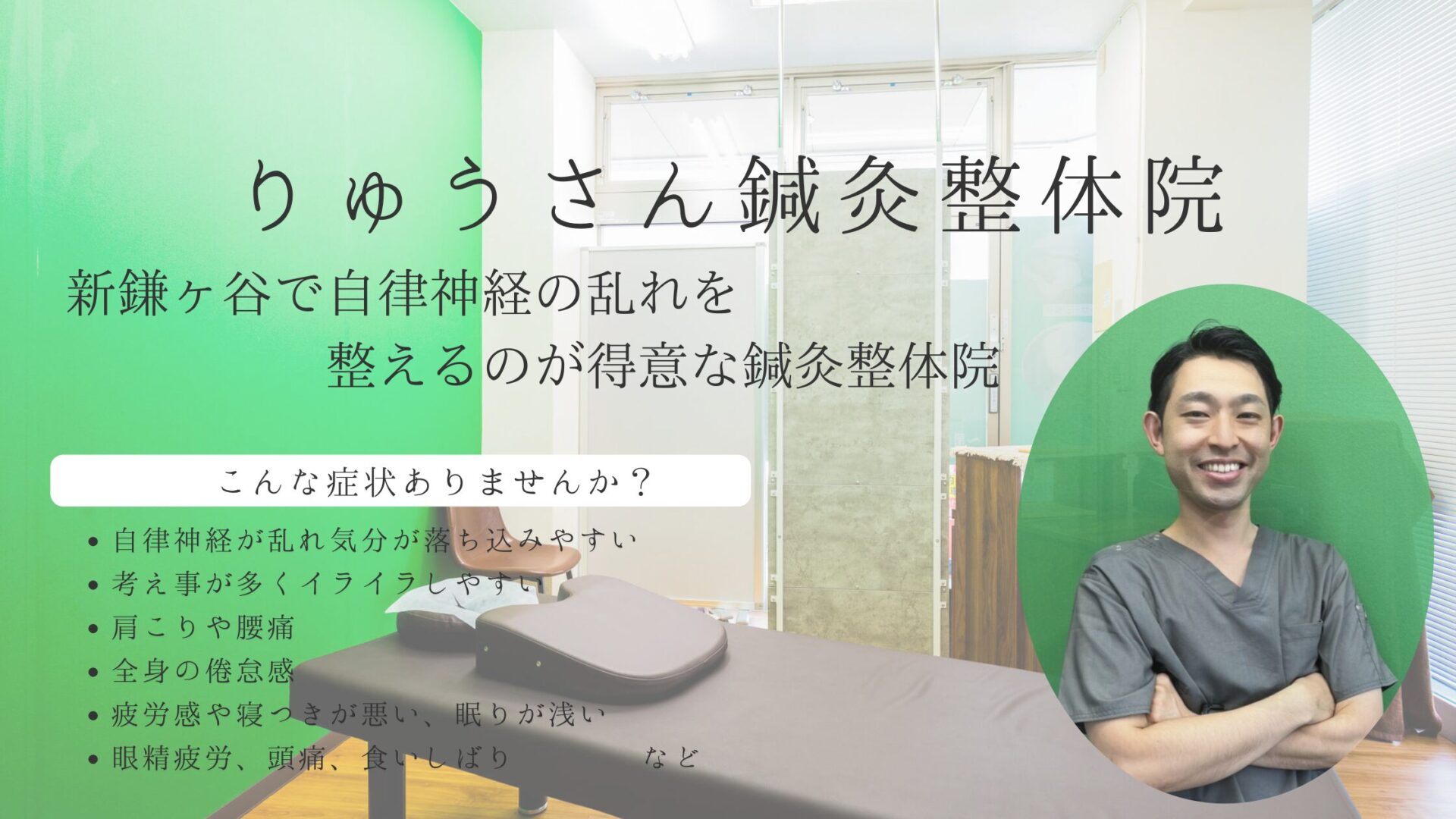1. 食品添加物とは?

食品添加物とは、食品の保存性を高めたり、味や見た目をよくするために使用される化学物質です。
食品表示のルールとして / 以降は食品添加物となります。
大きく分けると以下の種類があります。
- 保存料(ソルビン酸、安息香酸 など)
- 着色料(タール色素、カロチノイド など)
- 甘味料(アスパルテーム、スクラロース など)
- 香料(バニリン、リモネン など)
- 乳化剤(レシチン、ポリソルベート など)
- pH調整剤(クエン酸、リン酸塩 など)
これらの添加物は、一部のものを除いて通常の摂取量では安全とされていますが、長期間の摂取や過剰摂取により内臓や自律神経に影響を及ぼす可能性があります。

2. 食品添加物と内臓の関係
食品添加物が内臓に及ぼす影響は、肝臓・腎臓・腸が関係します。
① 肝臓への影響
- 解毒機能の負担
肝臓は体内に入った添加物を分解し、無害化する働きがあります。しかし、防腐剤や人工甘味料などの化学物質を長期間摂取すると、肝臓の負担が増し、解毒機能が低下することがあります。 - 脂肪肝のリスク
一部の人工甘味料(フルクトース・コーンシロップ)は肝臓で脂肪に変換されやすく、脂肪肝を引き起こす可能性が指摘されています。
② 腎臓への影響
- 過剰なミネラルの排出
リン酸塩などの添加物は、腎臓に負担をかけることがあります。特に腎機能が低下している人では、リンの過剰摂取が腎結石や骨密度の低下を引き起こす可能性があります。 - 人工甘味料の影響
一部の人工甘味料(スクラロース、アスパルテーム)は腎臓で代謝されずに排泄されるため、腎機能に悪影響を及ぼす可能性があるとされています。
③ 腸内環境への影響
- 腸内細菌バランスの乱れ
人工甘味料(スクラロース・アスパルテーム)や保存料は、腸内細菌のバランスを崩し、悪玉菌の増殖や腸の炎症を引き起こす可能性があります。 - 腸のバリア機能の低下
乳化剤(ポリソルベート80、カラギーナン)などは腸壁の粘膜に影響を与え、腸のバリア機能を弱めることで、リーキーガット症候群(腸もれ)を引き起こす可能性があるとされています。
3. 食品添加物と自律神経の関係
自律神経は、交感神経(活動モード)と副交感神経(リラックスモード)のバランスを保ち、内臓の働きを調整する役割を持っています。食品添加物はこの自律神経の働きにも影響を与えることがあります。
① 交感神経の過剰な刺激
- 合成着色料(タール色素)や人工甘味料は神経を刺激する
一部の合成着色料(赤色40号、黄色5号など)や人工甘味料(アスパルテーム)は、交感神経を過剰に刺激し、集中力の低下やイライラ、不眠などの症状を引き起こす可能性があります。 - アドレナリン分泌の影響
カフェインや一部の甘味料はアドレナリン分泌を増やし、交感神経を優位にするため、慢性的なストレス状態を作り出すことがあります。
② 副交感神経の低下
- 腸内環境の悪化が自律神経に影響
腸内細菌のバランスが崩れると、腸と脳をつなぐ「腸脳相関」の影響で、副交感神経の働きが低下し、胃腸の不調や便秘、下痢などの症状が出やすくなります。 - リン酸塩や防腐剤によるミネラルバランスの乱れ
リン酸塩がカルシウムの吸収を妨げることで、神経の興奮が抑えられず、不眠やイライラを引き起こすことがあります。
4. まとめと対策
食品添加物の影響まとめ
| 内臓・自律神経 | 影響 |
|---|---|
| 肝臓 | 解毒機能の低下、脂肪肝リスク |
| 腎臓 | ミネラルバランスの乱れ、腎結石リスク |
| 腸 | 腸内環境の悪化、リーキーガットの可能性 |
| 交感神経 | イライラ、不眠、ストレス増加 |
| 副交感神経 | 胃腸機能の低下、リラックスしづらい |
食品添加物の影響を減らすための対策
- 食品の選び方を工夫する
- 「無添加」「オーガニック」「自然食品」を選ぶ
- 加工食品の成分表示を確認し、不必要な添加物を避ける
- 特に合成着色料・人工甘味料・リン酸塩・保存料を多く含む食品を減らす
- 肝臓・腎臓の負担を減らす
- 水をしっかり飲む(老廃物の排出を促す)
- 緑黄色野菜や発酵食品を摂取(抗酸化作用&腸内環境改善)
- 適度な運動で代謝を促す
- 自律神経のバランスを整える
- 腸内環境を整える食事(発酵食品・食物繊維)
- リラックスする時間を作る(深呼吸・ストレッチ)
- カフェインや刺激物を控える
結論
食品添加物は短期的な影響は少ないですが、長期的に摂取すると内臓や自律神経に負担をかける可能性があります。
完全に避けるのは難しいですが、意識して選択することが健康維持につながります。